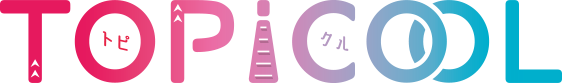Da-iCE工藤大輝 大切なのは「どうありたいか」 芸大イベントで語る

京都芸術大学オンラインイベントで講師を務めたDa-iCEの工藤大輝
Da-iCEの工藤大輝が14日、通学課程・通信教育課程あわせて約2万3000名が学ぶ日本最大級の総合芸術大学の京都芸術大学で特別イベントを行った。
同大学は、通信教育課程・音楽コースで「工藤大輝先生の楽曲制作を深掘りする」をオンラインで開催した。当初定員1000人で募集したが、想定を大きく上回る反応があり、急きょ申し込み枠を拡大。最終的に2100名を超える参加申し込みがあり、盛況のうちに幕を閉じた。
Da-iCE結成当時から、大手の会社に所属する他のグループとどう差別化するかを考え、自ら楽曲制作に取り組むスタンスを確立してきたという工藤は、音楽を“自分でつくる”ことへのこだわりを語った。SNSで「歌ってみた」「踊ってみた」動画が次々と拡散され曲が話題となる昨今において“どうバズらせるか”まで考えて制作することが時代のスタンダードだと解説しつつ、一番大切なのは「自分がどうありたいか」だと強調し、創作に通じる普遍的な姿勢を参加者に伝えた。また、100人いたら100通りの関わり方や正解がある音楽の世界。工藤は、「授業で話される内容に“刃向かう気持ち”を大切にしながら、それぞれの目指す音楽を追求してほしい」と、これから学ぶ受講希望者へメッセージを送った。
作詞・作曲の初心者には「自分の好きな音楽のコピーから始めるといいと思います。あえて“手が届かない”くらい、難しいものを選ぶのもおすすめです。突き詰めて、そのうち細部まで再現できるようになるといいですね」とアドバイス。「音楽を聴くときは、分析的に聴きますか?純粋に楽しんで聴きますか?」との質問には「ほぼ100%分析的に聴きます。このコード進行はあのパターンだな、この歌詞はどう構成されてるんだろう、と、楽曲制作を始める前からそんな聴き方をしていました。他のアーティストのライブを観ていても“俺だったらこうするな”と考えてしまうタイプです(笑)」と明かし、もし同大学に入学したら「音楽理論を学びたいですね。やってない自分が自信を持って言います。理論がわからなくても音楽を作れる。でも、理解したうえで作るほうが、きっともっと楽しいはずです」と話した。
この記事のフォト(1枚)
関連記事
-
- 記事
-
2025年11月12日 22時30分
Da―iCE 5年連続のアリーナツアーを完走「いつかドームに行けたら」
-
- 記事
-
2025年10月25日 21時29分
Da-iCE 花村想太「勝てなさそうな人が多くて…」 業界生き残りかけて、必死に編み出した独自スタイルにダメだし食らい苦笑い
-
- 記事
-
2025年10月22日 18時37分
Da―iCE アニメ「モンスターストライク」のOP主題歌「Monster」ノンクレジットオープニング公開
-
- 記事
-
2025年10月11日 15時30分
Da-iCE 花村想太「人生で食べたご飯で一番高かった…」 今、思い出しても“しびれる”会員制高級店で有名歌手にご馳走した逸品
-
- 記事
-
2025年10月08日 16時02分
Da-iCE 全国アリーナツアー開始 「Monster」配信リリースも発表
-
- 記事
-
2025年10月06日 20時32分
Da-iCE、結成14年目にして「情熱大陸」出演が決定!飛躍期した1年、リーダー手術の危機に直面したメンバー5人に密着